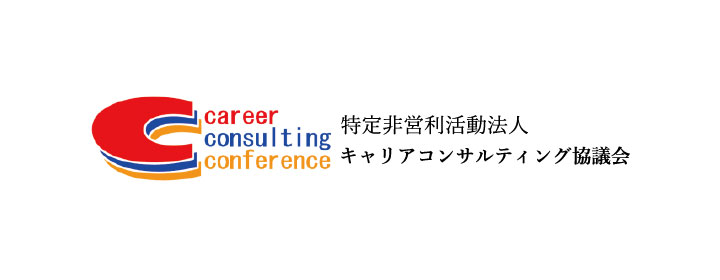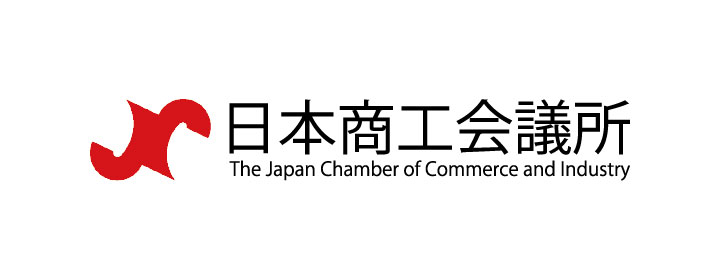◆最新・行政の動き
130万の壁対策 2年間で最大75万円
助成金に新コース 厚労省
厚生労働省は、「年収130万円の壁」による働き控えの解消に向けたキャリアアップ助成金の拡充案を明らかにしました。有期労働者などの社会保険の適用を進める観点から、当分の間の暫定措置として「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設します。
同コースは、令和8年3月末までの暫定措置として運用している社会保険適用時処遇改善コースに加えて新設するものです。社会保険適用時処遇改善コースが106万円の壁への対応として設けられているのに対し、新コースでは、年収130万円の壁も意識せずに働くことができる環境づくりを後押しします。
配偶者などの扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料の支払いが発生する130万円の壁は、106万円の壁に比べ、壁を超える際により多くの保険料負担が発生することから、労働者の手取り収入を増加させるためには大幅な労働時間の延長または額面賃金の増加が必要になります。
このため新コースでは、3年間で最大50万円を支給している社会保険適用時処遇改善コースを上回る助成額とします。有期労働者などが社会保険の適用を受ける際、労働時間の延長と賃金増加の組合せで労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主に対し、2年間で労働者1人当たり最大75万円を支援します。同助成金を拡充する雇用保険法施行規則の改正は7月1日施行予定です。
◆ニュース
体制整備を義務付け 熱中症の早期発見へ 改正省令公布
厚生労働省は4月15日、熱中症のおそれがある作業者の早期発見に向けた体制整備を事業者に義務付ける労働安全衛生規則の改正省令を公布しました。熱中症のおそれがある作業を行わせる際に、症状悪化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成しておくことも義務付けます。今年6月1日に施行します。
対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の場所で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われる作業。改正省令では、対象作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」や、「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ整備し、関係者に周知するよう事業者に求めます。
さらに、作業からの離脱や身体の冷却、医師の診察または処置を受けさせること、事業場における緊急連絡網および緊急搬送先の連絡先など、症状の悪化を防ぐための措置の実施手順を定め、関係者に周知することも義務とします。
賃上げ支援広がる 市町が支給金上乗せも 地方自治体
 物価上昇や人手不足を背景に賃上げの機運が高まるなか、中小企業の賃上げを支援する地方自治体の取組みが広がっています。
物価上昇や人手不足を背景に賃上げの機運が高まるなか、中小企業の賃上げを支援する地方自治体の取組みが広がっています。
群馬県では、従業員1人当たり5万円を支給する奨励金制度を新設します。太田市など県内4市町と連携し、県の支援金の受給企業に対しては、市町が1~2万円を上乗せ支援します。奨励金は、5%以上の賃上げを行った場合に支給します。支給上限は1事業所当たり20人まで。受付開始は7月上旬を予定しています。
栃木県も5月から、賃金を引き上げた従業員1人当たり5万円を支給する奨励金制度を開始しました。要件として、企業内男女間格差の是正につながる取組みの実施を設けます。たとえば、女性管理職の割合を昨年4月よりも高めるなどの取組みが対象となります。同県労働政策課は、「奨励金を機に、男女間の格差是正の機運も高めていきたい」と話します。令和6年賃金構造基本統計調査によると、同県の男性の所定内給与を100とした場合の女性の指数は74。全国で4番目に開きがある状態となっています。
大分県は、非正規雇用労働者や障害者の賃上げに焦点を当てています。国のキャリアアップ助成金のうち、正社員化コースと障害者正社員化コースを受給した企業に最大10万円を上乗せして支給します。両コースは、賃上げを3%以上行い、有期雇用労働者等を正社員化した場合などに支給される助成金。国と県の支給額の合計は、正社員化コースは最大90万円、障害者コースは100万円に上ります。
育休取得者増加で 部署全員へ応援手当 シャボン玉石けん
無添加石けんの製造・販売を行うシャボン玉石けん㈱は今年度から、産前産後休業・育児休業の取得者が出た部署のメンバー全員に、1人当たり月1万円の手当を支給します。部署のメンバーが10人を超える場合は、10万円を全員で等分します。「部署全体でフォローするという風土醸成を重視した」(同社広報担当)としています。
同社の各部署は10人前後のメンバーで構成されています。たとえば15人が在籍する部署で取得者が1人出た場合、14人に1人7000円ずつ支給します。支給期間は、取得者が復職するまで、あるいは新規採用や他部署からの応援などにより、人員補充が完了するまで。
同社では2014年以降、女性従業員の産休・育休取得後復職率は100%を維持しています。全体の約6割を占める男性従業員の取得も増加しており、今後も業務をフォローする従業員の負担増が見込まれることから、手当導入に踏み切りました。
保護者が仕事を確認 魅力発信へ見学ツアー 長崎県
長崎県は、高校生の保護者を主な対象にした地元企業の見学ツアーを開催します。バスで2~3社を回り、仕事内容や働いている従業員の雰囲気、社内の設備、周囲の環境などを確認してもらいます。
ツアーは、主に高校1~2年生の保護者を対象にしたもの。高校生自身や、大学生の参加も可能とします。昨年度は夏季と冬季に、1コース当たり2~3社を回るツアーを企画。計11コース(23社)に、104人が参加しました。今年度は保護者が参加しやすいよう、土曜日に開催するコースを増やし、より多くの保護者に対して地場企業の魅力発信を進めていきます。
同県未来人材課は、「高校生は保護者に就職先を相談するケースが多い。影響力が大きいので、保護者へのアプローチは効果的」と話します。昨年度参加した保護者からは、「職場の雰囲気を感じることができた」、「県内にこのような業種、企業があるとは知らなかった。子どもの将来の選択肢の参考になった」などの声が寄せられました。今年度も夏季と冬季の実施を予定しています。
同県の令和6年3月高校卒業者のうち、31.5%が県外に就職しています。4年は27.9%、5年は30.4%となり、微増傾向を示しています。
◆監督指導動向
屋内でも熱中症予防 死亡災害ゼロめざし運動 神奈川労働局
神奈川労働局は、管内で3年連続して熱中症による死亡労働災害が発生したことから、9月まで実施するクールワークキャンペーンの重点目標として、「死亡災害ゼロ」を掲げました。昨年は屋内作業中の労働者が亡くなっています。休業4日以上の労災の約3分の1も屋内で起きていることから、屋外だけでなく、屋内での熱中症予防対策の重要性を周知していきます。
昨年1年間の熱中症による死傷者数は78人に上りました(今年4月速報値)。10年前(18件)からは約4.3倍に増加しています。作業場所別の発生状況では、屋内作業が約3分の1を占めました。同労働局健康課は、「炉や厨房などの熱源がなくても、締め切った部屋や倉庫など、高温多湿の環境下で多発している」と危機感を示します。
運動期間中は、暑さ指数の適切な把握を呼び掛けます。冷房設備がなく風通しが悪い屋内作業については、環境省などが公表している地域別の暑さ指数を参考にするだけでなく、作業場での値を実測するよう求めていきます。
意識向上に向け、独自のキャッチコピー「Cool work KANAGAWA Mission ZERO」を設定し、ロゴマークも作成しました。管内労働基準監督署でステッカーを配布し、ヘルメットへの貼付けや社内掲示板での周知を促していきます。
◆送検
安全作業床未設置 隙間44cmから墜落死で送検 福岡中央労基署
福岡中央労働基準監督署は、昨年4月に労働者が足場から墜落死した労働災害に関連して、建具工事業者と同社部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検しました。労働者に高さ10.5mの場所で網戸とサッシを交換する作業を行わせるに当たり墜落防止措置を行っていなかった疑いです。
災害は、春日市の県営団地の改善工事現場で発生しました。労働者は、団地全体の古くなった窓の網戸とサッシを交換する作業を行っていました。地上から高さ約10.5mの5階部分で作業を行う際、足場と建物の間にあった44cmの隙間から墜落し、死亡しました。
同社は足場を設置していたものの、墜落を防止するために十分なものではなく、落下を防ぐネットなども設置していませんでした。
◆調査
「内定辞退あり」7割に 東京商工会議所調査
東京商工会議所は「2025年新卒者の採用・選考活動動向に関する調査」結果をまとめました。2024年12月末時点で、採用計画以上の25年新卒内定者数を確保している企業は13.4%でした。
内定・内々定者の状況について、「半数未満の辞退者がいる」と回答した企業の割合は47.4%、「半数以上の辞退者がいる」は25.7%となりました。合計すると73.1%の企業で、内定・内々定者が辞退しています。辞退者がいた企業の割合は、前年(67.4%)から5.7ポイント増加しました。
内定辞退防止に向けた取組みの実施状況を複数回答で尋ねています。回答が多い順に「採用担当者からの定期的な連絡」が68.0%、「内定式・内々定式」が60.5%、「採用担当者との懇談会」が47.4%、「会社見学会」が43.9%となりました。

25年1月以降も採用・選考活動を行う予定の企業は60.5%でした。1月が7.1%、2月が19.4%、3月が19.4%となり、活動が長期化している状況がうかがえます。
◆実務に役立つQ&A
育休給付いつまでか 支給期間途中で退職
![]() 育児休業期間中に退職することになった従業員がいます。こうしたケースは当社では初めてで、育児休業給付金の手続きで困っています。「最後の支給単位期間」について、給付金は支給されるのでしょうか。
育児休業期間中に退職することになった従業員がいます。こうしたケースは当社では初めてで、育児休業給付金の手続きで困っています。「最後の支給単位期間」について、給付金は支給されるのでしょうか。
![]() 育児休業給付金の支給日数は、原則30日間です(雇保法61条の7第6項)。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数ですが、ただし、期間の途中で離職した場合、喪失日の前日の属する期間の「前の期間」まで支給申請することができました。
育児休業給付金の支給日数は、原則30日間です(雇保法61条の7第6項)。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数ですが、ただし、期間の途中で離職した場合、喪失日の前日の属する期間の「前の期間」まで支給申請することができました。
令和7年4月以降にやむを得ず離職することになった場合は、離職日まで支給対象とする取扱いに変更されました。やむを得ない離職を対象としているのは、給付金を受給するためにはそもそも職場復帰が前提のためです(雇用保険業務取扱要領)。支給処理の都合上、当面の間は、離職日の前日まで支給し、1日分を追給するとしています(厚労省リーフレット)。なお、この取扱いは、令和7年4月1日以降に離職した被保険者に対して適用されます(雇用保険業務取扱要領)。この場合の支給申請は、支給申請期間の末日までなら可能としています。
◆身近な労働法の解説 ―事務所衛生基準~温度~―
事務所衛生基準規則では、事務所その他の作業場における労働者の清潔保持等のために事業者が講ずべき措置等について定めています。
その中で、「事務室の環境管理」に関して、4条および5条で事務室の温度について定めています。
1. 事務所の温度
 4条1項では、「事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない」としています。
4条1項では、「事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない」としています。
2項では、「事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない」とし、但し書きで、電子計算機等を設置する室における例外を定めています。
5条3項では、事業者の努力義務として、空気調和設備を設けている場合の室の気温と湿度について定めています。
2. 条文解説
4条1項では、室温が10℃以下の場合は暖房等により温度調節することを事業者の義務として定め、2項では、冷房する場合の室温について外気温より著しく低くしないことを定めています。
4条1項に違反したことで、労働安全衛生法23条(事業者の講ずべき措置等)違反に該当した場合には、罰則が設けられています(同法119条「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」)。
特別に室温を低くする必要があるサーバルームなどについては、2項但し書きで、電子計算機等を設置する室は、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りではないとしています。
5条3項では、「気温」について、エアコン等の空気調和(空調)設備を設けている場合は、労働者を常時就業させる室の気温が18℃以上28℃以下になるように努めなければならない、と定めています。なお、空調設備を設けている場合以外であっても、冷暖房器具を使用することなどにより事務所における室の気温は18℃以上28℃以下になるようにすることが望ましいこと、としています(令4・3・1基発0301第1号)。「湿度」については、相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない、としています。
3.その他
厚労省では、温熱条件について、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(平4・7・1労働省告示59号)を定め、「屋内作業場においては、作業の態様、季節等に応じて温度、湿度等の温熱条件を適切な状態に保つこと。また、屋外作業場については、夏季及び冬季における外気温等の影響を緩和するための措置を講ずることが望ましいこと」としています。労働契約法5条において、事業者には安全配慮義務が課されています。事務所内においても熱中症防止のための温度・湿度管理に留意し、作業内容を考慮した至適温度に設定するとよいでしょう。
◆今月の実務チェックポイント
―算定基礎届の交通費について―
毎年7月10日までに提出することになっている、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の提出時期が近づいています。今回は通勤手当について確認しましょう。
通勤手当は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
厚生年金保険法でいう報酬とは、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金、給料、手当などその名称にかかわらず対象になります。ただし、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(賞与)および臨時に支給されるものは除かれることとされています。
では、3カ月毎または6カ月毎に支払われる通勤手当はどうなるのでしょうか。
数カ月分を一括して支払われる場合は、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても「報酬」に含まれるものと取り扱われています。
したがって、事業所の給与規定に定めのある通勤手当は、労務の対償として受けるものであると認められ、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。3カ月分の場合は3分の1を6カ月分の場合は6分の1を各月に支払ったものとして算定します。
新型コロナウイルス感染症の影響や働き方改革の推進により、在宅勤務・テレワークを導入された企業も増えています。では在宅勤務・テレワークの場合、交通費の取扱いについてはどうなるのでしょうか。
当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱うとされています。
- 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれません。
- 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所の場合
当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。 なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、通勤場所・通勤経路の変更、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となります。
◆助成金情報
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
 「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に中小企業に助成するものです。
「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に中小企業に助成するものです。
本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
1 介護休業
介護支援プラン(※1)を作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させた場合
(※1)介護支援プラン:労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引継ぎの実施方法などを盛り込む
【主な要件】
① 介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知★1
② 労働者との面談を実施し、プランを作成・実施★2
③ 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
2 介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)※2
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇などの仕事と介護の両立ができる制度を利用させた場合
(※2)介護両立支援制度:所定外労働の制限制度・時差出勤制度・深夜業の制限制度・短時間勤務制度・在宅勤務制度・フレックスタイム制度・法を上回る介護休暇制度・介護サービス費用補助制度
【主な要件】
① ★1および★2の実施
② いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日までに継続雇用
3 業務代替支援
介護休業取得者および短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)または業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合
【主な要件】
① 新規雇用
対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入れで確保
② 手当支給等
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用し、業務代替者への手当支給等
【支給額】
| 種別 | 要件 | 支給額 | ||
| 1 | 介護休業 | 対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 | 40万円 | |
| 2 | 介護両立支援制度 | A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 | 20万円 | |
| B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 | 25万円 | |||
| 3 | 業務代替支援 | 1)新規雇用 | 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入 | 20万円 |
| 2)手当支給等 | A:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給 | 5万円 | ||
| B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 | 3万円 | |||
(※)支給額は、休業取得/制度利用者1人当たり。1~3それぞれ1事業主5人まで。制度利用期間に応じて増額あり。
詳細な要件および申請方法等は 厚生労働省HP等をご参照ください。
◆今月の業務スケジュール
| 労務・経理 | 慣例・行事 |
| ・5月分の社会保険料の納付 ・5月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付・固定資産税(都市計画税)(第1期分)の納付 ・労働保険の年度更新 申告・納付(6月2日から7月10日) |
・男女雇用機会均等月間 ・男女共同参画週間 ・外国人労働者問題啓発月間  |