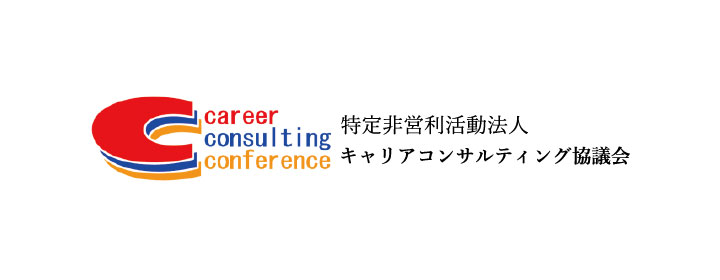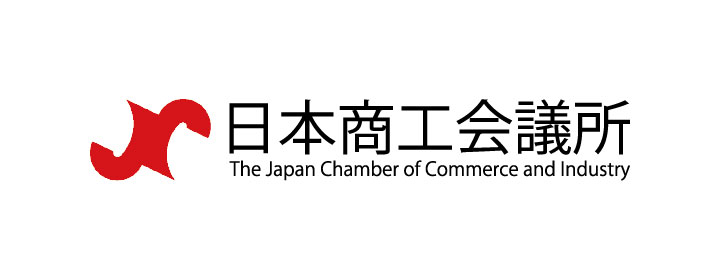最新・行政の動き
養育両立支援休暇 時間単位で取得が可能 短時間労働者でも 厚労省
 厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出しました。
厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出しました。
改正法では、今年10月以降、事業主に対し、同措置として、養育両立支援休暇の付与や、始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度などから2つ以上の措置を選択して講じるよう義務付けています。
通達では、柔軟な働き方を実現するための措置のうち、テレワーク等について、情報通信技術を利用しない業務も含むことを明確化しました。
養育両立支援休暇は、1年間に10日以上与え、具体的な用途を限定せずに利用できるようにする必要があります。利用例として、通常保育所に子を迎えに行く配偶者が出張で迎えができない日に、時間単位で休暇を取得し、保育所に迎えに行くケースを示しました。
1年間の起算日は事業主が任意に定められるとしました。同休暇の取得単位については、改正法で「1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、1日未満の単位(省令により時間単位)で取得することができる」と規定している一方、省令には規定がないため、労働者の所定労働時間数に関係なく、1時間単位で取得できるとしています。ただし、業務の性質または業務の実施体制に照らして、時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者は、労使協定により、時間単位での取得ができない者と定めることができるとしました。
失効年次有給休暇の積立を、同休暇の付与措置として講じることができる点も明確化しました。
ニュース
経過措置でリーフレット くるみんの新認定基準 厚労省
厚生労働省は、「くるみん認定」の新認定基準が今年4月から適用されるのを受け、認定申請の経過措置などに関するリーフレットを作成しました。令和6年度末までに開始した行動計画については、7年度以降の計画期間を、新基準を達成しているかどうかを判断するための計画期間とみなすことができるとしました。この場合、新基準達成による認定マークが付与されます。また、9年3月末までに申請を行った場合は、計画期間の時期にかかわらず旧基準の認定を受けられるとしています。
新たな認定基準では、育児休業等取得率などに関する要件を厳格化しました。3段階の認定のうち、たとえば「くるみん」では、男性の育休等取得率の基準を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げています。
リーフレットでは経過措置の適用例も示しました。5~8年度の4年間を計画期間とする企業において、5~6年度の男性育休対象者が25人で取得者が計4人、7~8年度の対象者が30人で取得者が計10人の場合、5~8年度全体の育休取得率は30%に満たないものの、7~8年度に限れば33%に上るため、経過措置により新基準による認定を受けられるとしています。
訪問先の情報収集を 在宅ケアハラスメントで 福岡県・マニュアル
 福岡県は、在宅医療および在宅介護現場における利用者や家族からの暴力・ハラスメントに対し、事業所として取り組むべきことを示したマニュアルを公表しました。訪問先の情報を収集し、間取りや、周囲に助けを求められる場所などを事業所内で共有することが有効としています。マニュアルに併せて、未然防止策として、従業員から利用者に渡すことを前提としたリーフレットも作成しました。暴力やハラスメントの例を紹介しています。県内の約9500事業所に直接配布し、活用を呼び掛けています。
福岡県は、在宅医療および在宅介護現場における利用者や家族からの暴力・ハラスメントに対し、事業所として取り組むべきことを示したマニュアルを公表しました。訪問先の情報を収集し、間取りや、周囲に助けを求められる場所などを事業所内で共有することが有効としています。マニュアルに併せて、未然防止策として、従業員から利用者に渡すことを前提としたリーフレットも作成しました。暴力やハラスメントの例を紹介しています。県内の約9500事業所に直接配布し、活用を呼び掛けています。
同県が令和5年3月に実施した調査によると、在宅医療・介護従事者の約4割が暴力やハラスメントを受けた経験がありました。なかには「包丁を突き付けられる」など生命の危機を感じた事例もみられています。
マニュアルでは、「日ごろからの備え」、「発生時」、「発生後」、「契約解除」の4段階に分けて、事業所が取り組むべき事項を解説。日ごろからの備えでは、訪問先の情報収集のほか、契約時に利用者に統一した説明ができるようにするための従業員教育が必要としました。
発生後は、客観的な記録を残すよう求めました。在宅医療や介護は密室で行われ、他者から見えにくいという特性があることから、報告書の書式を定めておくと、事業所内の全従業員が同じ基準で記載できるとしています。
賃上げで10万円加算 人材確保の支援金拡充 北海道
北海道は、人手不足が深刻な事業者の人材定着を後押しするため、新たに人材を採用し、一定期間以上雇用している事業者を対象とした支援金制度を今年3月から拡充します。すでに雇用している労働者の月給を前年度から3.5%以上引き上げたなどの場合に、支給額を10万円加算する仕組みを設けます。社内の処遇改善を促し、求職者へのアピールにつなげます。
対象は、運輸業や建設業、宿泊業、飲食サービス業、介護施設など、道内で人手不足が顕著な業種において、運転者などの職種で採用した場合とする予定。離職期間が1カ月以上の求職者を、今年3~6月の間に31日以上雇用した事業者に対し、支援金10万円を支給します。さらに、前年度から3.5%以上の賃上げを行った場合、または離職期間が1年以上の人材を新たに雇用した場合には、10万円の加算金を支給。支援金と併せて、事業者は最大20万円を受給できます。支援金は、約200事業者に支給する見込みです。
監督指導動向
代休の見直し促す 割増賃金で相談めだつ 高崎労基署
群馬・高崎労働基準監督署は、管内事業場へ代休と休日の振替の適正な運用を呼び掛けるため、リーフレットを作成しました。割増賃金の考え方については、カレンダーを用いて視覚的に分かりやすく解説しています。同労基署の担当者は、「労働者から割増賃金の支払いに関する相談を受ける際に、代休と休日の振替を誤って運用している事業場がみられる。今一度、運用を見直してほしい」と話しています。
カレンダーでは、法定外休日が土曜、法定休日が日曜、賃金締日が月末、週の起算日が日曜の会社を例に挙げました。日曜に出勤を求めたケースを想定しています。休日の振替の場合、休日労働に対する割増賃金は不要ですが、週の法定労働時間を超えた場合は通常の賃金の2割5分以上の割増賃金が発生するため、注意を促しました。
休日の振替を行うに当たって必要な措置もまとめています。就業規則に振替休日の規定を置いたうえで、振替休日は4週4日の休日が確保される範囲内に与えるよう求めました。振替休日を特定したうえで、前日までに労働者への通知が必要と注意しています。
昇降時“三点確保”を 死亡災害増え点検票 福岡労働局・運送業向け
 福岡労働局は、陸上貨物運送事業で昨年1年間に発生した死亡災害が前年比倍増の8件に上ったことから、災害防止対策状況を点検するチェックリストを作成し、管内事業場に活用を促しています。過去の災害事例に基づき、「荷台での昇降時には、両手両足4点のうち、3点で身体を支える“三点確保”を実行しているか」など、合計13項目を設けました。
福岡労働局は、陸上貨物運送事業で昨年1年間に発生した死亡災害が前年比倍増の8件に上ったことから、災害防止対策状況を点検するチェックリストを作成し、管内事業場に活用を促しています。過去の災害事例に基づき、「荷台での昇降時には、両手両足4点のうち、3点で身体を支える“三点確保”を実行しているか」など、合計13項目を設けました。
陸上貨物運送事業とは、トラック事業者や倉庫事業者などの事業者を指します。事故の型別では、荷台からの「墜落・転落」、「交通事故」、
フォークリフトによる「はさまれ・巻き込まれ」でそれぞれ2件ずつ死亡災害が発生しています。
点検表では、事故の型別にチェック項目を設けました。墜落・転落においては、荷台作業時は安全な昇降設備を使用しているかなど、4項目を挙げています。
交通事故防止に向けては、運転者の十分な睡眠時間に配慮した労働時間管理を行っているかの確認を求めました。同労働局安全課は、「昨年発生した交通事故の死亡災害では労働時間管理上の問題はみられていないが、大きな事故につながる可能性もあるので、事業者には注意をしてもらいたい」と話しています。
送検
溶接の火花が引火 爆発災害で製造業送検 但馬労基署
兵庫・但馬労働基準監督署は、昨年10月に発生した爆発により労働者が負傷した労働災害に関連して、金属製品製造業者と同社工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで神戸地検に書類送検しました。引火性の防錆材が発した蒸気が残存していたにもかかわらず、アーク溶接の火花を接近させた疑いです。
爆発は、コンベアの部品製造現場で発生しました。災害発生前、労働者は箱型の部品内部に、引火性のキシレン等を含む防錆材を塗装し、塗装箇所に蓋をしていました。2時間半後に蓋を溶接するため、蓋に乗りアーク溶接作業を行ったところ、火花が防錆材の蒸気に引火。蓋ごと吹き飛ばされて床面に落下し、背骨と両足を骨折する休業約半年のケガを負いました。
同労基署によると、防錆材を塗った箇所に蓋をしている場合、引火性のある蒸気が抜けるまでに、本来は半日~1日ほどかかるといいます。
調査
45%がスポットワーク経験 派遣社員WEBアンケート調査
一般社団法人日本人材派遣協会は、昨秋インターネット上で行ったアンケート調査をまとめました。「現在派遣で働いている」と回答した5245人のうち、45.0%がスポットワークを経験していることが判明しました。その際の就業形態を尋ねたところ、「アルバイト」が25.7%で最も多く、「派遣」が22.9%で続いています。
スポットワークをした理由は、「追加収入を得るための副業として」(54.9%)や、「休日や夏休みなど都合の良い時にできる」(45.9%)が多く、「すぐに収入が得られるため」(30.4%)、「面接などがなくすぐに仕事に就けるため」(24.4%)なども挙がっています。
図表 スポットワークをした理由

スキルアップのために取り組んでいることを尋ねた設問では、「派遣会社の開催する研修やeラーニングに参加している」が24.8%で最も多くなりました。一方で、「何もしていない」が4割以上を占めています。有期労働契約者と無期労働契約者で回答の傾向に大きな差はみられなかったものの、「通信教育や教材などを使って自分で勉強している」割合は、有期(19.9%)が無期(14.5%)より5.4ポイント高くなっています。身に着けたいと思う専門的・技術的なスキルは、「AI・機械学習」が20.4%(昨年比7.9ポイント増)で最多となりました。
実務に役立つQ&A
賞与支給どう明示? 正社員登用する可能性
 アルバイトとして採用しますが、将来、正社員登用する可能性があります。契約期間内に賞与の支給日はありませんが、仮に正社員になれば支給対象となりそうです。賞与の支給有無は、どのように明示すれば良いでしょうか。
アルバイトとして採用しますが、将来、正社員登用する可能性があります。契約期間内に賞与の支給日はありませんが、仮に正社員になれば支給対象となりそうです。賞与の支給有無は、どのように明示すれば良いでしょうか。
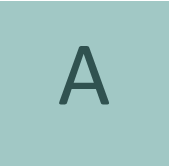 パート・アルバイトを雇い入れたときに明示しなければならない事項に、賞与の有無があります(パート・有期雇用労働法施行規則2条)。原則として、賞与は、支給されない可能性がある場合でも、制度が存在するなら「有」と明示することが必要としています(平31・1・30雇均発0130第1号など)。
パート・アルバイトを雇い入れたときに明示しなければならない事項に、賞与の有無があります(パート・有期雇用労働法施行規則2条)。原則として、賞与は、支給されない可能性がある場合でも、制度が存在するなら「有」と明示することが必要としています(平31・1・30雇均発0130第1号など)。
パート・有期雇用労働法のQ&Aにおいては、契約期間内に要件を満たさないため適用がないときには、「無」と明示することが可能としています(令4・3・31雇均有発0331第1号)。パートらで有期雇用契約を反復更新する場合には、契約更新の都度明示の有無を判断することになるでしょう。
なお、期間の定めのない正社員として労働契約を締結する際、賞与に関する定めがある場合には、明示が必要です(労基則5条1項5号)。
身近な労働法の解説 ―前借金相殺の禁止―
労基法17条では、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定めています。
1.前借金相殺の禁止とは
 本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し、金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するという趣旨で設けられています(昭63・3・14 基発150号)。
本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し、金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するという趣旨で設けられています(昭63・3・14 基発150号)。
労働することを条件として労働者に金銭を貸し付け、賃金から一方的に天引きする形で返済させることによって、労働者の足留め策や強制労働の原因となるため、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」と「賃金」を相殺することを禁止しています。
本条の「賃金」は、労基法11条の賃金ですので、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものです。
本条は、前借金そのものを禁止している訳ではなく、賃金と前借金の相殺について、使用者側で一方的に行うことを禁止しています。使用者からの貸付金は、労働者の自由意思に基づく相殺や別個の返済契約に従って返済してもらうことになります。
なお、前借金により、返済完了まで労働することを義務付ける等、労働を強制することは、労基法5条(強制労働の禁止)に違反すると解されています。
2.前借金その他労働することを条件とする前貸の債権とは
「前借金」(ぜんしゃくきん)とは、労働契約の締結の際またはその後に、労働する(将来の賃金により弁済する)ことを条件として使用者から借り入れた金銭のことです。
「その他労働することを条件とする前貸の債権」は、前借金のほか前借金に追加して労働者や親権者などに渡される金銭で、前借金と同様、金銭貸借関係と労働関係が密接に関連し、身分的拘束を伴うものです。
労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融・生活資金など、明らかに身分的拘束を受けないものは、本条の債権に該当しません(昭22・9・13 発基17号、昭33・2・13 基発90号)。
3.本条違反
本条に違反して、前貸しの債権と賃金を相殺した場合には、使用者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(労基法119条1号)。
また、本条の債権と賃金を相殺(賃金控除)した場合は、本条違反だけでなく、控除分の賃金未払いとなり、労基法24条(賃金の支払)違反が成立します。
今月の実務チェックポイント
社会保険の随時改定が必要になるシーン
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動、賃金体系の変更があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。
・転居などにより通勤手当の額に変動があった場合
通勤手当も毎月決まって支給する給与として固定的賃金に含まれます。
随時改定において、3カ月または6カ月毎に支給され、その期間で分割し割り切れない場合は原則最初の月に端数を含めます。
・在宅勤務およびテレワークの場合
労働契約上の労務の提供の場が自宅か事業所かにより異なります。
- 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれません。
- 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合
当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。 なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となります。
・産前産後休業・育児休業等の長期休職中、一定期間、基本給等の給与は支払われるが通勤手当が不支給となっている場合
通勤の実績がないことにより不支給となっているだけで、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、随時改定の対象とはなりません。
助成金情報
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
「在籍型出向」とは、出向元企業と出向先企業の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、出向先企業に一定期間継続して勤務することをいいます。
「在籍型出向」では、自社にはない実践での経験による新たなスキルの習得が期待でき、企業の事業活動の促進に効果的です。
労働者のスキルアップを在籍型出向で行い、条件を満たした場合には、出向元事業主に対しての助成金が支給されます。
【助成対象となる出向】
・労働者のスキルアップを目的とすること
・出向した労働者は、出向期間終了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること
・出向から復帰後6カ月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること。
【助成の内容】
対象:出向元事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
| 中小企業 | 中小企業以外 | |
| 助成率 | 2/3 | 1/2 |
| 助成額 | 以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで) イ 出向労働者の出向中の賃金(※)のうち出向元が負担する額 ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額 |
|
| 上限額 |
8,635円(毎年8月改正)/1人1日当たり |
|
※出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要あり
【助成額の算出例】
条件例
・出向元は中小企業
・出向前の賃金日額、出向中の賃金日額はいずれも9,000円
・出向元賃金負担5,400円、出向先賃金負担3,600円(出向元の賃金負担が6割)
・出向復帰後の賃金日額9,450円
助成率:2/3
助成額:3,000円(上限額の条件である8,635円以下も満たしている)
イ:5,400円
ロ:4,500円(9,000円×1/2)となるため、低い額はロとなり、
具体的な金額は 4,500円×2/3=3,000円
【受給までの流れ】
1.出向元事業主と出向先事業主との契約(出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の賃金などの負担割合などを取り決める)
労働組合などとの協定、出向予定者の同意
2.出向計画届(スキルアップ計画を含む)提出・要件の確認(出向元事業主が出向計画届を作成し、出向開始日の前日(可能であれば2週間前)までに都道府県労働局またはハローワークへ提出)
3.出向の実施(1カ月間~2年間)※助成金の対象となる支給対象期間は、出向開始日から起算して1年が経過する日(当該日までに出向期間が終了する場合は当該出向期間終了日)まで
4.出向から復帰(賃金上昇※復帰後6カ月間の各月においていずれも5%以上)
5.支給申請
6.助成金受給
※ 制度の詳細は厚生労働省HP・事業主のための雇用関係助成金の「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)」をご参照ください。
今月の業務スケジュール
| 労務・経理 | 慣例・ 行事 |
| ●2月分の社会保険料の納付 ●2月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 ●前年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで) ●贈与税の申告・納付(2月3日から3月17日まで) ●36協定の更新・届出 |
●春の全国火災予防運動 ●入社式の準備  |