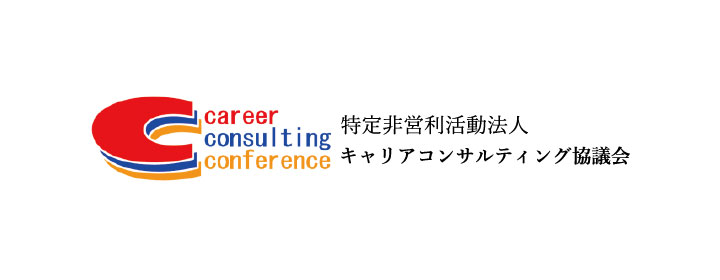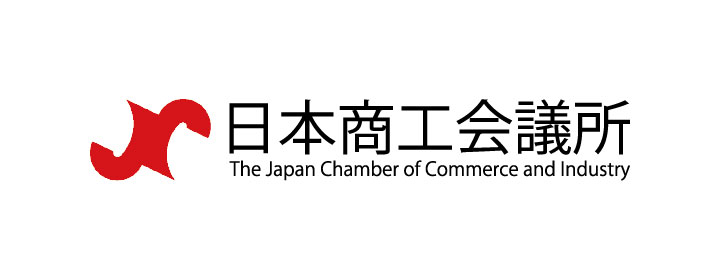最新・行政の動き
個人事業者業務上災害
注文者に報告義務課す 安衛則改正案・厚労省
厚生労働省は、建設業の一人親方など個人事業者の業務上災害の報告制度の創設に向け、労働安全衛生規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けました。令和9年1月に施行する予定です。
昨年5月に公布された改正労働安全衛生法および作業環境測定法では、個人事業者などの業務上災害報告制度の創設を盛り込みました。個人事業者の業務上災害を網羅的に把握する仕組みがなかったことから、報告制度により、効果的な労働災害防止施策などの検討につなげるのが狙いです。報告主体や報告事項などの詳細については、省令などで示すこととしていました。
改正省令案要綱によると、個人事業者と同一の場所で仕事を行う直近上位の注文者(特定注文者)に対し、労働者と同一の場所で作業を行う個人事業者が業務に起因する負傷・傷病によって4日以上休業したことを把握したとき、所轄労基署に遅滞なく報告するよう義務付けます。罰則は設けません。特定注文者が存在しない場合には、災害発生場所を管理する事業者が報告義務を負います。
被災者である個人事業者が災害発生の事実を伝達できる場合には、個人事業者本人が特定注文者または管理事業者に遅滞なく報告する必要があります。報告を受けた事業者は、必要事項を補足したうえで労基署に遅滞なく報告しなければなりません。
脳・心臓疾患および精神障害事案については、本人が直接、労基署に報告できることとします。
ニュース
建設など8分野は2年 育成就労の転籍制限期間 入管庁案
外国人技能実習制度に代わって令和9年4月に開始される育成就労制度を巡り、出入国在留管理庁と厚生労働省は、分野ごとの転籍制限期間に関する案を有識者会議に提示しました。外国人本人の意向で職場を移る「転籍」を制限する期間について、建設や工業製品製造、飲食料品製造、介護など8分野で、就労開始から2年としました。宿泊や物流倉庫、ビルクリーニングなど9分野は1年での転籍を可能とします。
今年3月に閣議決定した基本方針では、「転籍制限期間については、1年とすることをめざしつつ、当分の間、育成就労産業分野ごとに、業務内容を踏まえて、1年から2年までの範囲内で分野別運用方針において設定する」としています。1年を超える期間を設定する分野の受入れ企業は、原則として、分野ごとの基準を満たす待遇向上策を講じなければなりません。
出入国在留管理庁などの案では、各分野の制限期間をその理由とともに示しました。たとえば、建設分野では、外国人が安全に作業を行えるようになるために、一定の時間をかけて安全衛生教育を行う必要があることなどを理由として、2年に設定しました。
政府は、分野別運用方針について、年内の閣議決定をめざしています。
店長年収2000万円へ 部下の満足度で評価 トリドールHD
㈱トリドールホールディングスは、運営するうどんチェーン「丸亀製麺」の店長職をアップグレードし、主な役割を従業員のハピネス(満足度)の最大化と顧客の感動づくりに設定します。新役職「ハピカンキャプテン」は4段階で処遇し、最上位では年収2000万円に到達可能としました。ハピネスについては、音声対話型生成AIによるヒアリングで測定します。
従来の店長の年収は520万円が上限となっていました。新役職のキャプテンは500万円を下限とし、3年で300人体制をめざします。そのうち10人程度は最上位の2000万円クラスとなることを見込んでいるとしました。
キャプテンにはハピネス向上のため、従業員の誕生日を祝ったり、交流会を開く予算を与えます。従業員や顧客と直接触れ合う機会を増やすため、シフト作成・発注管理、帳簿管理などの管理業務は副店長に移管します。
顧客の感動度は、食後に記入してもらうアンケートの結果から分析し、スコア化します。
電子申請1月開始へ 適用・給付関連が可能に 協会けんぽ
全国健康保険協会(協会けんぽ)は来年1月から適用・給付関連の電子申請サービスを始める方針を明らかにしました。協会けんぽのホームページまたは今後リリースするスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」で申請ができるよう現在準備を進めています。
 利用対象者は被保険者、被扶養者、社会保険労務士で、被保険者と被扶養者はマイナンバーカードで本人確認をします。社労士はユーザーIDとパスワードの事前取得により利用できるようになります。受付け時間は平日の8~21時。
利用対象者は被保険者、被扶養者、社会保険労務士で、被保険者と被扶養者はマイナンバーカードで本人確認をします。社労士はユーザーIDとパスワードの事前取得により利用できるようになります。受付け時間は平日の8~21時。
対象の申請は傷病手当金、出産手当金、高額療養費などの給付と、任意継続被保険者資格の得喪などの適用にかかるもの。スマホから申請書を選択し、情報を入力すれば、オンラインで手続きが完結します。申請後は「受付け」「審査中」「審査完了」「返戻」などの進捗状況が随時確認できます。返戻となった場合は返戻理由のお知らせと申請ファイルが送られてきます。申請ファイルは再申請の際に利用可能としました。
リリース後は段階的に機能を拡充し、将来的には健診・各種申請の勧奨やヘルスリテラシーの提供、健康づくりアドバイスなど、プッシュ型の支援を実現したい考えです。
採用活動の悩み共有 意見交換する場提供へ 福島県
 福島県は、採用担当者が他社の採用担当者とつながる機会となるイベントとして、「オフサイトミーティング」を初めて開催します。他社とかかわりを持つ機会の少ない採用担当者に対し、採用活動の悩みを共有したり、解決策を模索したりする場を提供します。イベントは11月11日、県庁講堂で対面にて開催します。
福島県は、採用担当者が他社の採用担当者とつながる機会となるイベントとして、「オフサイトミーティング」を初めて開催します。他社とかかわりを持つ機会の少ない採用担当者に対し、採用活動の悩みを共有したり、解決策を模索したりする場を提供します。イベントは11月11日、県庁講堂で対面にて開催します。
イベントでは、自社の取組みを紹介し合う時間を設けます。グループワークやフリートーク形式で行い、取組みの経緯や効果を気軽に質問し合える場にする予定です。
同県はこれまで、セミナーなどで県内企業の好事例を発信してきました。イベントは、セミナー参加者からの「他社とざっくばらんに話したい」との声を受けてのもの。30社の参加をめざしています。
同県雇用労政課は、「首都圏への若手の流出など、県内企業が抱える課題は共通点も多い。今後の採用活動のヒントを得る機会になってほしい」と参加を促しています。
送検
下水道作業員2人が溺死 警報周知せず送検 相模原労基署
神奈川・相模原労働基準監督署は、下水道工事で下請の労働者2人が雨水に流され死亡した労働災害に関連して、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)違反の疑いで横浜地検相模原支部に書類送検しました。下水道管内に大量の水が流れ込んだ際の警報を、関係請負人に周知していなかった疑いです。
同法に基づく労働安全衛生規則では特定元方事業者に、作業場所に水が流れ込むおそれがある場合、警報を定め周知することを義務付けています。
災害は昨年9月19日に発生しました。現場には下請3社が入場し、下水道の耐震補強工事に従事していました。同社では日頃は赤色灯とトランシーバーを警報として使っていましたが、事故発生前にトランシーバーに不具合が発生。口頭での警報に変更したが、下請に周知していませんでした。
作業中、突如として大雨が発生。下水道管内で作業していた複数の労働者へ口頭で避難指示が行われましたが、2人が逃げ遅れました。
監督指導動向
無期転換周知を強化 高齢者の雇用機会増で 愛媛労働局
愛媛労働局は、管内企業の高齢者雇用の機会増加を受け、有期労働契約の無期転換ルールに関する周知を強めています。同ルールの第二種計画認定に基づく特例に関して、要件や必要となる手続きに関する問合せが多く寄せられていることから、同労働局のホームページ内に「無期転換ルール」に関する特設ページを作成。同ルールの特例を中心に解説しています。
定年後に引き続き雇用される有期契約労働者は、雇用主が第二種計画認定を受けていると、特例により無期転換申込み権が発生しません。同労働局管内では、人手不足を背景に、定年後の再雇用だけでなく、高齢者を新規で雇用する企業が増えています。同労働局雇用環境・均等室によると、他社で定年まで働いていた労働者を新たに雇用する場合も、特例の適用対象になるとの誤解が多いといいます。
令和6年4月に義務化された、無期転換に関する事項の条件明示についても周知を徹底していきます。同労働局が平成28年から実施している無料のコンサルタント派遣事業などを通じて、同ルールに関する情報発信を行っていくとしました。
調査
時間的制約が実施課題に 経営者の学び直しに関するアンケート調査結果
東京商工会議所は中小企業の経営者における学び直しの状況を調査しました。
学び直しに現在取り組んでいる割合は50%でした。2~3年以内に取り組みたいと回答した割合は20%となっています。回答率1.8%(回答数446件)を踏まえ、「実際の取組み状況は、この結果よりも低い水準にあることが推測される」と分析しています。
学び直しに取り組むうえでの課題を複数回答で尋ねています。現在取り組んでいない経営者では、「時間が確保できない」が最も高く、53%に上りました。「現時点で必要性を感じない」が35%、「学び直しが必要な知識・スキルがわからない」が32%で続きます。現在取り組んでいる経営者でも、時間的制約を課題に挙げる者が多くなりました。「時間的拘束が長く、業務に支障がある」が45%、「現状で課題となることはない」と「費用負担が重い」がともに30%となっています。

実務に役立つQ&A
共働きでも受給可能か 業務上災害の遺族年金
 従業員が業務上災害で亡くなり、労災保険給付を請求することになったため、会社も協力します。この従業員は夫婦共働きですが、遺族補償年金の受給に必要な生計維持関係は認められるのでしょうか。
従業員が業務上災害で亡くなり、労災保険給付を請求することになったため、会社も協力します。この従業員は夫婦共働きですが、遺族補償年金の受給に必要な生計維持関係は認められるのでしょうか。
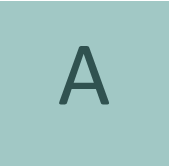 遺族補償年金を受けることができるのは、死亡した労働者が生計を維持していた遺族に限られます(労災法16条の2第1項、則14条の4)。配偶者も対象です。
遺族補償年金を受けることができるのは、死亡した労働者が生計を維持していた遺族に限られます(労災法16条の2第1項、則14条の4)。配偶者も対象です。
生計維持関係は、労働者の死亡当時、その収入によって日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であったかどうかにより判断します(労災保険給付事務取扱手引)。
労災保険の生計維持関係は、もっぱらまたは主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要しないため、労働者の収入により生計の一部を維持されていれば足り、いわゆる共稼ぎも含まれます(昭41・1・31基発73号)。相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないとされています(平2・7・31基発486号)。
身近な労働法の解説 ―情報機器作業における労働衛生管理③―
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)では、事務所における情報機器作業を行う環境の整備方法について、照明及び採光を定めています。
1.照明及び採光に関するガイドライン
(1)室内は、できる限り明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。
※ 室内の照明及び採光については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない(事務所衛生基準規則第10条第2項参照)。
(2)ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300 ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。
また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。
 ※ 「書類上及びキーボード上における照度」とは、書類やキーボードなどに入射する光の明るさをいう。
※ 「書類上及びキーボード上における照度」とは、書類やキーボードなどに入射する光の明るさをいう。
「ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさとの差はなるべく小さくすること」とは、瞳孔は明るさに応じてその大きさを調節しており、一般的に、ディスプレイ画面や書類・キーボード面と周辺の明るさの差が大きいと眼の負担が大きくなるので、なるべく明るさの差を小さくすべきであるという趣旨である。
(3)ディスプレイ画面に直接または間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインドまたはカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
(4)間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。
※ 「グレア」とは、視野内で過度に輝度が高い点や面が見えることによっておきる不快感や見にくさのことで、光源から直接または間接に受けるギラギラしたまぶしさなどをいう。
(5)その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。
※ 情報機器作業従事者がディスプレイを注視している時に、視野内に高輝度の照明器具・窓・壁面や点滅する光源があると、まぶしさを感じたり、ディスプレイに表示される文字や図形が見にくくなったりして、眼疲労の原因となる(眼の明るさに対する調整は網膜の順応や瞳孔の大きさによって行われるが、強い光に対する調整が優先されるためにグレアがあると比較的暗い画面上の文字等は見にくくなる)。
また、これらがディスプレイ画面上に映り込む場合も同様である。したがって、ディスプレイを置く位置を工夫して、グレアが生じないようにする必要がある。
映り込みがある場合には、ディスプレイ画面の傾きを調整することなどにより、映り込みを少なくすることが必要である。
一般にグレアを防ぐために、近い視野内での輝度比は1:3程度、広い視野内の輝度比は 1:10程度が推奨されている。
その他の映り込みを少なくする方法としては、フィルターを取り付ける等の方法があるが、フィルターの性能によっては、表示文字の鮮明度が低下したり、フィルター自身の表面が反射したりすることがあるため、反射率の低いものを選ぶ等の注意が必要である。
今月の実務チェックポイント
年末調整の準備
 年末調整の準備を始める季節になりました。
年末調整の準備を始める季節になりました。
年の途中で新たに採用された方について、国民年金保険料を納付されていた場合は、会社に「令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の提出を依頼しましょう。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
所得税法上および地方税法上ともに控除対象のため、その年の所得税だけでなく、翌年の住民税にも影響します。
最近は、e-Taxで利用できる電子データの送付もできるようになっています。郵送よりも早く受け取ることができるようです。また、マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることができます(電子送付希望の登録を行うと、登録後は書面の郵送が停止されます)。
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
【保険料控除申告書の送付スケジュール】
- 令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
電子送付:令和7年10月中旬から下旬にかけて順次送付予定
郵 送:令和7年10月下旬から11月上旬にかけて順次送付予定
2.令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(の対象者は除きます。)
電子送付:令和8年1月下旬から順次送付予定
郵 送:令和8年2月上旬送付予定
保険料控除証明書は被保険者ご本人宛に送付されますが、配偶者やその他の親族の社会保険料を納めたときにも、保険料控除証明書を提出することにより、所得控除の対象になります。
令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に納付された方については、年末調整には間に合いませんので、ご自身で3月15日までに確定申告で提出することができます。
生命保険料、損害保険料の控除証明書だけでなく、中途採用者の方には国民年金保険料の納付があれば提出して頂くようにしましょう。
助成金情報
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)
本コースは、いわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者として就職が困難な方の安定した雇用促進をはかることを目的に、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の要件を見直し、拡充したものとなります。
いわゆる就職氷河期世代を含む中高齢者の方々の中において、
・不安定な仕事に就いている(正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている)方
・仕事に就いておらず(無業状態である)、就職にお悩みの方
・学校卒業後、正規雇用として経験がない方であって、子育てなどにより就業にブランクがある方
などの方々を、正規雇用労働者として採用いただくことへの支援として、特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)が創設されました。
【支給額】対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します。
| 合計助成額 | 支払い方法 |
| 60万円(50万円) | 30万円(25万円)×2期 |
・かっこ内は大企業に対する支給額
【対象となる労働者】
雇入れの日において①~⑤のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介で正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を助成します。
- 35歳から60歳未満の方
- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者等として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方
- 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
- ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
【対象となる事業主】
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
- 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと
- 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
- 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳、当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿などを整備・保管していること
【雇い入れから支給申請までの流れ】
- 求人の申込
ハローワークからの紹介などを経由
2.対象労働者の雇い入れ
3.助成金の第1期支給申請
労働局・ハローワークによる支給・不支給決定(第1期)
4.助成金の受給(第1期)
5.助成金の第2期支給申請
労働局・ハローワークによる支給・不支給決定(第2期)
6.助成金の受給(第2期)
*制度の詳細は厚生労働省HP特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)のご案内等をご参照ください。
今月の業務スケジュール
| 労務・経理 | 慣例・ 行事 |
| 10月分の社会保険料の納付
10月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 3月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税の中間申告・納付 |
お歳暮の準備・発送 秋の全国火災予防運動 労働時間適正化キャンペーン 職業能力開発促進月間 |